キュウリは他の夏野菜と違って、意外と収穫時期が短いです。
ナスやピーマンは、上手く育てれば秋口まで収穫が続きますが、キュウリは一度にドサッと獲れて、数か月で終了するイメージです。
もしも、時期をずらして種まきをすれば、夏の間ずーっと、キュウリを食べ続けられると思うのですが、種から育苗するのにも手間がかかるため、なかなか計画通りに育てることができません。
・・・そう思いながら、キュウリの脇芽を剪定していて、思いつきました。
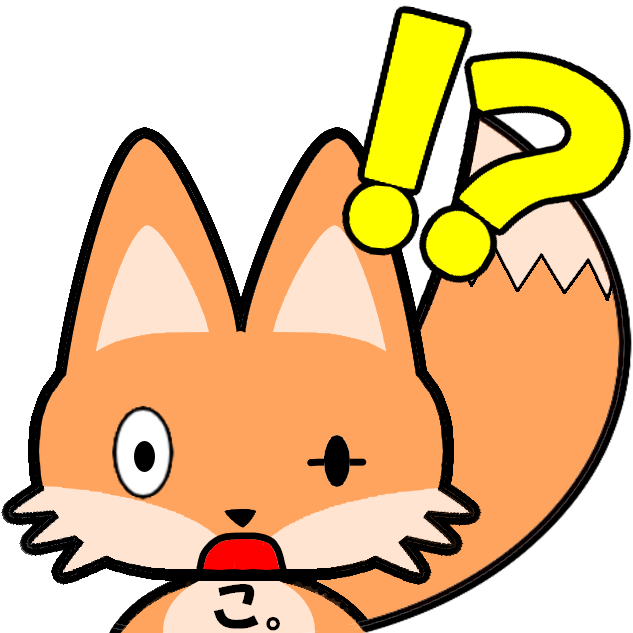 こんこっと。
こんこっと。この脇芽を「挿し芽(挿し木)」で増やすことができれば、ずーっとキュウリを収穫できるんじゃないの?
ただし、キュウリが挿し芽で簡単に増やせるのかどうかは、分かりません。
そこで、実際に試してみました。
キュウリの挿し芽に挑戦する
脇芽をカッターで切って、すぐに水に漬けます。








プラカップに鹿沼土(細粒)もしくは赤玉土(細粒)を入れて、育てます。
底には、軽石(小粒)を入れています。
ちなみに、右の2つは小玉スイカの挿し芽です。小玉スイカも挿し芽で根付くか、確かめてみます。


乾燥が怖いので、ケースに入れて湿度を高めにし、直射日光の当たらない、明るい日陰で育てます。


翌日、かなり萎れてて、ビックリです!


水を、追加しました。
直射日光には当てていませんが、連日30℃を超える猛暑なので、挿し芽には厳しいかもしれません。




鹿沼土と比べて、赤玉土の挿し芽は、比較的元気です。
用土の保水性の違いだと思います。
分かりにくいですが、蒸散を抑えるために、大きな葉はハサミで半分に切りました。




4本中2本は大丈夫そうですが、残りの2本は厳しいです。


よく見ると、赤玉土の挿し穂の地際から、根が出ていました。
根は、葉を取り除いた「節」から出ています。










4鉢中3本で、発根しました。成功です。
ただし、夏風邪をひいてしまい、しばらく観察していなかったので、実際はもっと早く発根していた可能性が高いです。
キュウリの発根の追加情報




十字に切れ目を入れた中から、発根している様子が観察できます。
あと、切れ目を入れていない茎の側面からも、発根しているようです。


上の写真は、挿し芽とは別に、種まきをして間引きした芽です。
ハサミで茎を切ったものが、たまたまメダカの水槽に落ちて自然に発根していました。
意外とキュウリは発根しやすい植物のようです。






発根の様子を観察するために、追加で、水挿しの実験をしてみました。
根はいろんな場所から出ますが、発根のしやすい順に、「①節の部分 > ②切り口 > ③茎」のようです。
(節の部分から出ている黄緑色の細長いのは、切り忘れた「ツル」です。根は白色です。分かりにくくて、ごめんなさい;;)






小玉スイカの挿し芽も試していたのですが、2本中どちらも発根していました。
今日の教訓



今回分かったポイントを踏まえて、もう一度、「キュウリの挿し芽(完全版)」を試そうと思ったのですが、もっといい方法を思い付きました。
次は、挿し芽ではなく、その方法を試してみたいと思います。
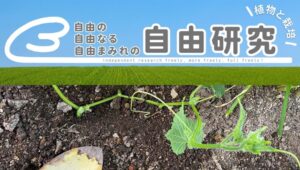
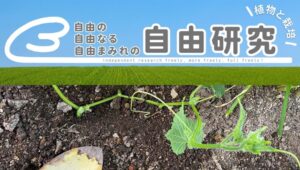
今日はここまで。
ではでは、またね。


コメント